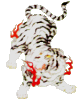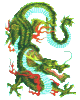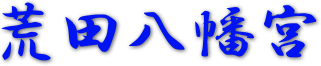

|
|
 |
| 鹿児島市の下町で近くに国立大学もある若者の街「荒田」(あらた)の八幡様「荒田八幡宮」です。神社に面した道路には今でもチンチン電車が走っており、この神社名と同じ電停もあり誠に風情のある町並みです。わたしも小さい頃から馴染みの深い神社であります。 こちらは、八幡宮でありますが「大隅正八幡」鹿児島神宮の御分社であります。 八幡様は日本一のお社数ともいわれ県下でも様々な八幡様がみられますが神宮の分社ということでは異質な存在であるといえましょう。鹿児島神宮(大隅正八幡宮)の西の守り神として御分社されました。 もともとこのあたりは荒田村と呼ばれ八幡宮となる天文21年(1552年)までは地元の氏神様であり八幡神以外の神様が鎮まってらっしゃました。 島津家十五代当主「島津貴久公」により現在の御社域に再興されましたがそれから500年近く八幡大菩薩としてこの地の守り神となっています。 |
 |
 |
 |
 |
| この地に島津貴久公が再興されたときに植樹されたとされる御神木樹齢は500年あまり幹回り約5mあるそうです。右上は「八幡浜くだり」の時に担がれる神輿が三基納めてあります。右下は手水舎。 |
 |
| 拝殿は極彩色の配色と彫刻の美しいお社。老朽化に伴う修繕はされているもの 度重なる戦火も運良く、くぐり抜けて約460年前の社殿がそのままです。 |
 |
 |
 |
 |
| 荒田八幡宮の境内社です。右上「権現さあ」(事解男命)「三宝荒神」「恵比寿神」 「田の神さあ」(地元信仰の農耕の神)「水神」「門守神」などが祀られております。 |



荒田八幡宮の東西南北の四方を囲むように「四随神」が存在する。 現在ではその風習はなくなっているようですが、2年毎の春のお彼岸に神輿を担いでこの随神をめぐる。いずれも荒田八幡の近辺にこの祠は存在するようだが残念ながら筆者「ハヤチ」は未だ確認しておりません。どのような経緯でこの神事があっていつ頃からやらなくなったかも不明。ただ、数少ない関連資料を参考にするなかで見えてきたのは、親神様である鹿児島神宮ではその御社の東西南北を守護する為に荒田八幡を含めた四分社(正若宮八幡、投谷八幡、鹿児島大明神)がある。これに似せたものであるかとも考えたが荒田八幡の四隋神はむしろ御分社される以前、つまり「荒田村」であったころにこの地の地元神の頃の御神事であり、荒田八幡宮を中心にしてその東西南北を御神域と想定してこの四随神が存在したように思われます。特定されている神様も八幡神でなくその方位の守りについて最適な神様を御配置された感があり、これから考えてもどうも風水思想が見え隠れするような感じです。 いずれにしても推測の域を脱しないので今後も引き続き調べて見ようと思います。 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|